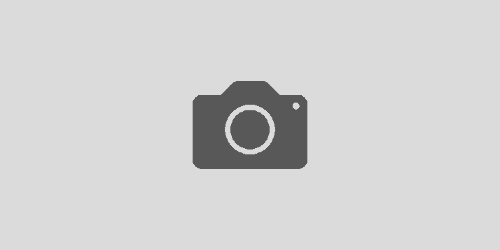弁理士試験に挑戦中の奴が特許法第一章を整理してみた
本投稿は、知財に関わったことが無く、まだ勉強して半年も経過していない初学者が自分なりに
特許法第1章総括を整理したものである。
故にこの投稿に記載されていることが必ずしも正しいとは限らない。
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
特許法の目的である。特許といわれると保護の規定が多く、利用を図る規定が少ないことから
特許法は権利者の保護を目的とするものだと思われがちである。
しかし特許法は第一条にある通り、産業の発達に寄与することが目的であり、
新規発明公開の代償により発明を奨励し、その発明の利用を図る側面もある。
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
特許法の二条では言葉の定義をしている。
特許権は独占排他権である為、どこまでが権利範囲なのかを明確にする必要があった。
そこで法は曖昧な概念である実施、特許発明、発明を再定義した。
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。(期間の延長等)
二条と同様に特許権は独占排他権である為、いつまで特許権が存続しているのか、
その他、権利侵害や出願時期、手続きや